理事長あいさつ

学校法人福岡女学院理事長 廣田 りょう
福岡女学院は1885年(明治18年)福岡美以美教会(現在の福岡中部教会)にてキリスト教による英和女学校として開校いたしました。皆様のおかげにより、現在ではキリスト教精神を基盤として幼稚園、中学校、高等学校、大学、看護大学、大学院までの、総合的な女子教育機関として、本年創立140周年を迎えるに至りました。
本学院の近況といたしまして、中学・高校においては高校新校舎の完成に続き、本年7月には新たな学びの場として中学校新校舎が完成予定であり、運動部や音楽コンクールの全国大会などでも多くの生徒が活躍しています。また幼稚園は創立70周年を迎え、自然あふれる環境の中で幼子を育み、入園前の子育ての方々、地域の方々などへの様々な子育て支援も継続しています。大学における2025年3月卒業生の就職状況は、航空関連や金融保険をはじめとした様々な業界、公務員、教職など多方面にわたり人材を輩出いたしております。さらに看護大学においては多くの卒業生が大学病院や総合病院などに、看護師として早期に内定し就職しております。加えて、本学院内での高校から大学・看護大学への進学や、幼稚園行事における高校音楽科生徒による演奏など、本学院ならではの学校連携を強化しております。
幅広い関係者の意見の反映や逸脱した業務執行の防止を趣旨とした改正私学法が施行され、さらに風通しの良い法人運営の強化も進めております。歴史と伝統を踏まえたうえで、140周年さらに150周年を見すえて、常に新しい福岡女学院をご覧いただけるよう、役員・教職員一同努めてまいりますので、皆様の変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
2025年4月
学校法人 福岡女学院
理事長 廣田 りょう
院長あいさつ

学校法人福岡女学院院長 守山 惠子
創立140周年を迎えて
福岡女学院は1885年に、キリスト教に基を置く学院として福岡の地で産声を上げました。今年、2025年は創立から140年の節目の年となります。
創立者のジェニー・ギール宣教師、共に力を尽くしてくださった方々、その後、平穏な時にも苦難の時にもバトンを落とさずにつないでくださった方々、さらにそれを支えてくださった多くの方々の日々のお働きと祈りがあったからこその140年だと、深い感謝をもって振り返っております。
世界を見渡せば、そしてごく身近なところでも、お互いを傷つけあうようなできごとが続いています。福岡女学院は、学院に連なる一人一人が社会に優しさや喜びを届け、平和をもたらす役割を果たしたいと願います。
福岡女学院の働きのために、地域の方々、同窓生はじめ多くの方々からお力添えをいただいていることに心から感謝をいたします。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
福岡女学院はこれからも歴史に学び、未来を見据え、祈りつつ、大切なことを見失わずに教育の業に励むことを通して、社会に貢献いたします。
2025年4月
学校法人 福岡女学院
院長 守山 惠子
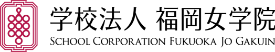
![理事長・院長あいさつ[test]](https://www0.fukujo.ac.jp/houjin/wp-content/uploads/2021/12/mainph-greeting.png)